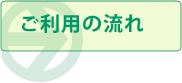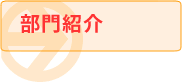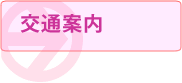- TOP>
- ニュース・お知らせ
療育講演会の質問事項への回答4
岩波幼稚園 園長 岩波先生からのコメントの後半です。
⑧幼稚園の入園を希望する場合、必ず未就園児教室に参加し、発達障害であることを伝えた方が受け入れる側としてはよいですか?早く伝えすぎると入園拒否されたりしないか心配です。
難しい問題です。受け入れる側としては、未就園児教室に必ず参加するかどうかはともかく、状況を伝えるという観点においては、そのほうが絶対によいと思います。理由は受け入れた後の対応について、充分保護者の方とお話をして双方が納得してスタートできるからです。
ただ我々としては、発達障害のお子さんを受け入れるにしても限度があります。残念ながら1クラスに何人も発達障害のお子さんがいると、たとえ補助者をつけてもクラス運営が難しくなります。また昨今、いわゆるグレイゾーンのお子さんも多くなってきています。そうなるとどこかで区切りをつけなければならなくなります。例えば家が近い方優先とか、先着順とか紹介者がある方優先とかそういうふうになります。またそうなると、正直に相談した方が断られて、黙っていた方が入るという矛盾も起こりえます。さらには、園によってはやんわりとお断りするところもあるかも知れません。そうなると、早く伝えすぎると入園拒否されたりしないかという心配が現実味を帯びてきます。
しかしこれも個人的意見ですが、入園拒否をするような園には入園しないほうが結果としていいと思います。入園拒否するような園は、受け入れ態勢が整っていないか、受け入れてもちゃんと対応する自信がないからという場合もあります。そんなところにお子さんを入れてもかわいそうなだけです。しっかりとお話をして、どのようにそのお子さんを育んでいくのか双方が納得して入園するほうが、よほどお子さんのためだと思います。
ただし、ここで問題なのは、発達障害のお子さんの人数とそれを受け入れる園のキャパシティーが合わなくなってきているという点です。早急にすべての園で受け入れできる体制を整えるのはもちろん、特別支援教育の助成を充実させる必要があると考えます。
⑨卒園後、高学年になってから出てきた問題は、どんなことでしたか?
たくさんあります。勉強がついていけない、教師やクラスメイトに対する反抗的態度、いじめの対象となる、登校拒否、家庭内暴力、虐待などなど。その他本人と担任と学校と親がバラバラになって、複合的な問題になる場合もあります。そうなってから療育センターなどに行ってもなかなか難しいです。しかし、早い段階から少なくともそういう療育機関と関わっていれば、たとえ長く途切れていた後でも対応や修復は早いような気がします。
多分彼ら彼女らは、発達の特性も省みられず、ずっと周りからただちゃんとしろ、しっかりしろ、やれば出来るはずだ、出来ないのは弛んでいるからだ、人に迷惑をかけるな、あるいは親の育て方が悪い、父や母が悪い、いや祖父や祖母が悪い、などと延々とやってきているわけです。きっと自分はダメな人間だと思ってしまうのも無理ないかも知れません。
⑩発達障害児と定型発達児をうまく関わらせるコツがありましたら教えてください。
これは適切な例がすぐには浮かびません。日々試行錯誤の連続です。年中少ぐらいでは、あまり配慮しなくとも子ども同士でうまく関わっていってくれる場合が多いです。また子ども達は、あれこれ言わなくてもどんどん発達障害の子どものサポートをしてくれます。または発達障害を理由にいじめたりすることは、まず幼稚園期では殆どありません。
ただ、年長ぐらいになると、やっぱりちょっと違うなという思いが周りにも出てくる場合があります。この時、子どもに発達障害の概念を説明しても当然わかってはもらえないので、違うことばで話すこととなります。大概はお友達一人ひとりが違っていても何も不思議でないのと同様に、当該児がちょっと違っていてもそれが不思議ではないというように持っていく場合が多いです。あの子は変わっているからとか幼いからとか、あかちゃんだからという説明は避けたいです。できればみんなが自然に関わっていながらかつ違和感がないというのが理想です。
ただし、突然たたく、人のものを壊すなど人に迷惑をかける行動の場合は難しいです。「○○ちゃんだけ何でいいの?」と言われると説明に困ります。その場合は、皆が納得するように当該児にもきちっと言うことも必要になってきます。
それから一般的にも言えることですが、そのお子さんのよいところを見つけて褒めて伸ばしてあげるということも大切だと思います。発達障害のお子さんは、苦手なことが多い場合もありますし、苦手の度合いが極端な場合も多いです。しかし、得意なこともあります。そこを保育者が見つけて認めてあげて、また周囲の子ども達とともにも認め合ってあげることで、当該児のクラスでの居場所や存在感を確保してあげるということもひとつの方法かと思います。
でもあまり大人が偉そうなことを言わなくても、結構子どもって色々と考えて関わりを持っているんだなというのが、正直なところでもあるのです。
⑪保護者間同士のトラブルや園として困ったことが、今までのご経験の中でありましたら教えてください。
何に関しての保護者同士のトラブルなのか、園で困ったことなのか、分からないのでお答えできないのですが、発達障害に関しての保護者同士のトラブルやそれに関連して園で困ったことということであれば、ほとんどありませんでした。たとえば○○ちゃん(発達障害のお子さん)がうちの子をたたいて困るなどというご相談を受ける場合もありますが、これは幼稚園としてあるいは保育者として対処すべき問題と考えますので、発達障害ということとは関係なく、ご相談いただいた方に納得していただけるための方法を園として考えご提案し実行します。
ただ発達障害児の保護者と園がうまく行かなかったということは結構あります。理由は、方針や考え方の違い、当方の配慮不足やその他ちょっとした行き違い、ことばのあや、誤解などです。
⑫幼稚園の先生方は、「発達障害児の知識」を深める努力をされていますか?市内の他園を含めて・・・。
大なり小なり研修などを受け努力していると思います。しかし、市内の他園の具体的な実情はわかりません。
横須賀市や療育相談センターにおいても発達障害に関する教職員対象の研修を行っていただいているのを始め、横須賀市私立幼稚園協会では、県の連合会などと協力して、統合保育講座、発達障害に係るオープン講座などに教職員を派遣しています。
また一部の園では、発達支援コーディネーターの講習を受けた教員も配置しています。
⑬入園後、障害が疑わしいと気づいても、親が認めないときはどうしたらいいのでしょうか?
先に述べましたとおりです。いきなり話をして、ああそうですかとは行きません。まずよく保護者の話を聞くことだと思います。話をしていくうちにこの先生ならここまで話してもいいやとか、もしくはポロッと本音が出る場合もあります。また話す際は、如何にその子が保育者にとって気になるか、あるいは如何にこちらがその子に対して困っているかという視点では極力話さず、保護者の方がどう思うかどう感じているか、どういうふうに困っているかなどの視点を中心に話すとよいかと思います。そして、最終的に保護者自身が育てづらさに気付いたり、うちの子やはりちょっと気になるなと思っていただければ、その後色々な展開につなげていくことが出来ます。
それでも認めない、あるいは気づいてくださらない場合は、今のところはしょうがない、と思うしかないです。「卒園後何かあったら言ってくださいね」と送り出します。言ってくる場合もありますしない場合もありますが、ない場合が多いです。
これも個人的な印象ですが、今後発達障害に関しては、「診断は遅めに、支援は早めに」というのが主流になってくると思います。そうなると、親が認めるか認めないかという重要性は後退してくる可能性はあります。認めるか認めないかよりも、早い段階で周りがそのお子さんの状況を共有してどのように接してあげられるのかを考えることの方が重要だと思うのです。二次虐待(と思われる周囲の対応)の可能性を排除するということを大前提とした上で、時間をおくことはひとつの選択肢になってくるかも知れません。
ただし、個人的な感覚として、もう少し先の話になるかもしれません。時代がまだそこまで行っていないような気もするのです。でもいずれはきっとそうなってきますし、早くそうなってきてほしいと思っています。
しかしそうなると、幼稚園に関しては今の支援制度では対応ができなくなる恐れがありますので、早急に新たな支援システムを構築するなど対策が必要だと思います。今の支援制度は、認めるということが前提に成り立っている制度だからです。だから子どもの状態や気持ちとは関係なく、認めるか認めないかということが最重要課題となってしまい、関係者が苦悶するのです。これは非常に重要な問題で、声を大にして申し上げたいです。
⑭支援がうまくいっていると思われる具体例をいくつか伺いたいです。
具体的事例の記載になりますと、本人特定が出来てしまう可能性もありますので、当該保護者の了解を取らずにお話するのはやめておきます。
⑮入学に際し保護者から通常級か支援級の選択を相談をされた時のアドバイスや配慮されていることがありますか?
本人にとって何がいいのかを第一に考えます。しかし、我々や保護者が本人にとって一番いいと思っても、それが本当に本人にとってもいいのかはまた別問題ですので、そこが難しいところです。また我々と保護者の見解が分かれることも多いです。
ケースバイケースですが、保護者が迷っていられれば支援級を勧めます。なぜならその方が手厚く見ていただける可能性が高いからです。私はよく半分冗談ですが、普通級は飛行機のエコノミークラス、支援級はエグゼクティブクラスのようなものですよ、と言ったりします。あんなぎゅうぎゅうなところより、ゆったり広々お世話する人も沢山いて、どちらがあなたのお子さんに対して手厚いですか、と。いずれにしろ支援級に対する偏見はなくしていかなければと思います。
また進学後普通級でうまくいかなくて支援級に移るということは、本人にとって挫折感につながる恐れがあります。それは避けたいと思っています。逆に最初は支援級に行っても、通級などをしながら結果として普通級に移る場合もあります。その方が本人にとっては楽だと思います。
そういったことをお伝えしています。
※以上、岩波先生から頂いた原稿をそのまま掲載しました。
これで先生方からのコメントの掲載は終了です。